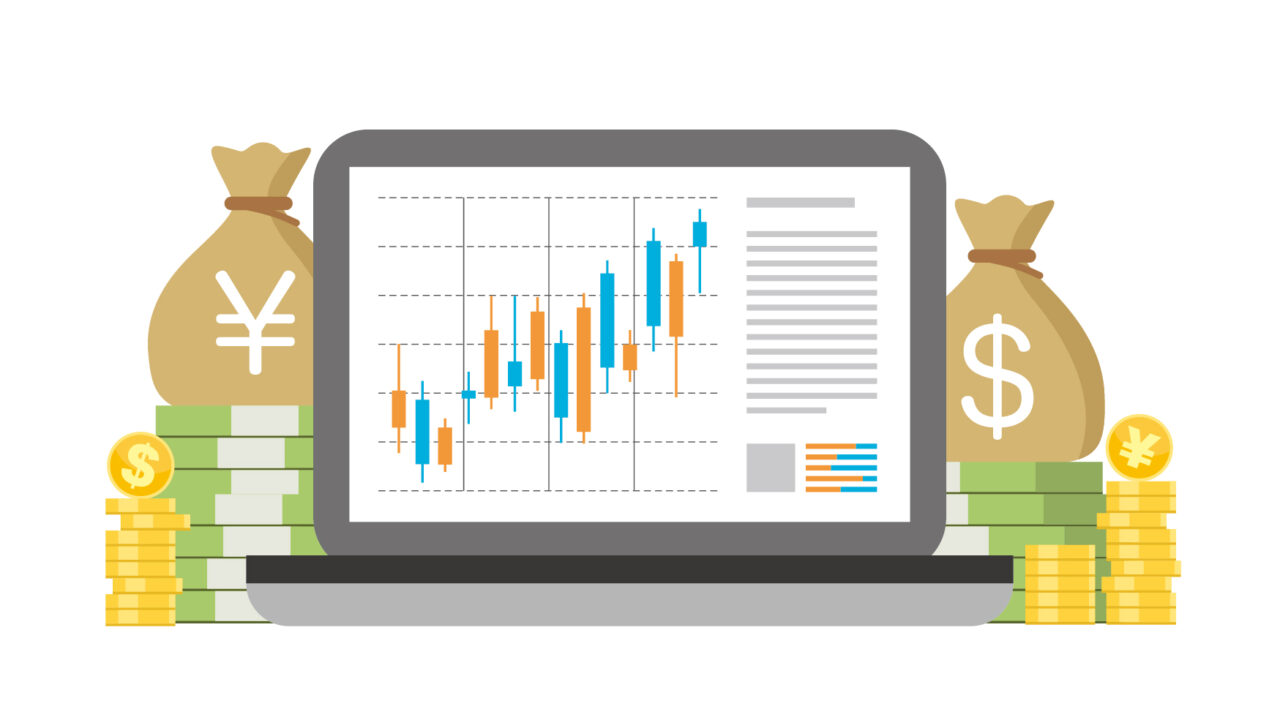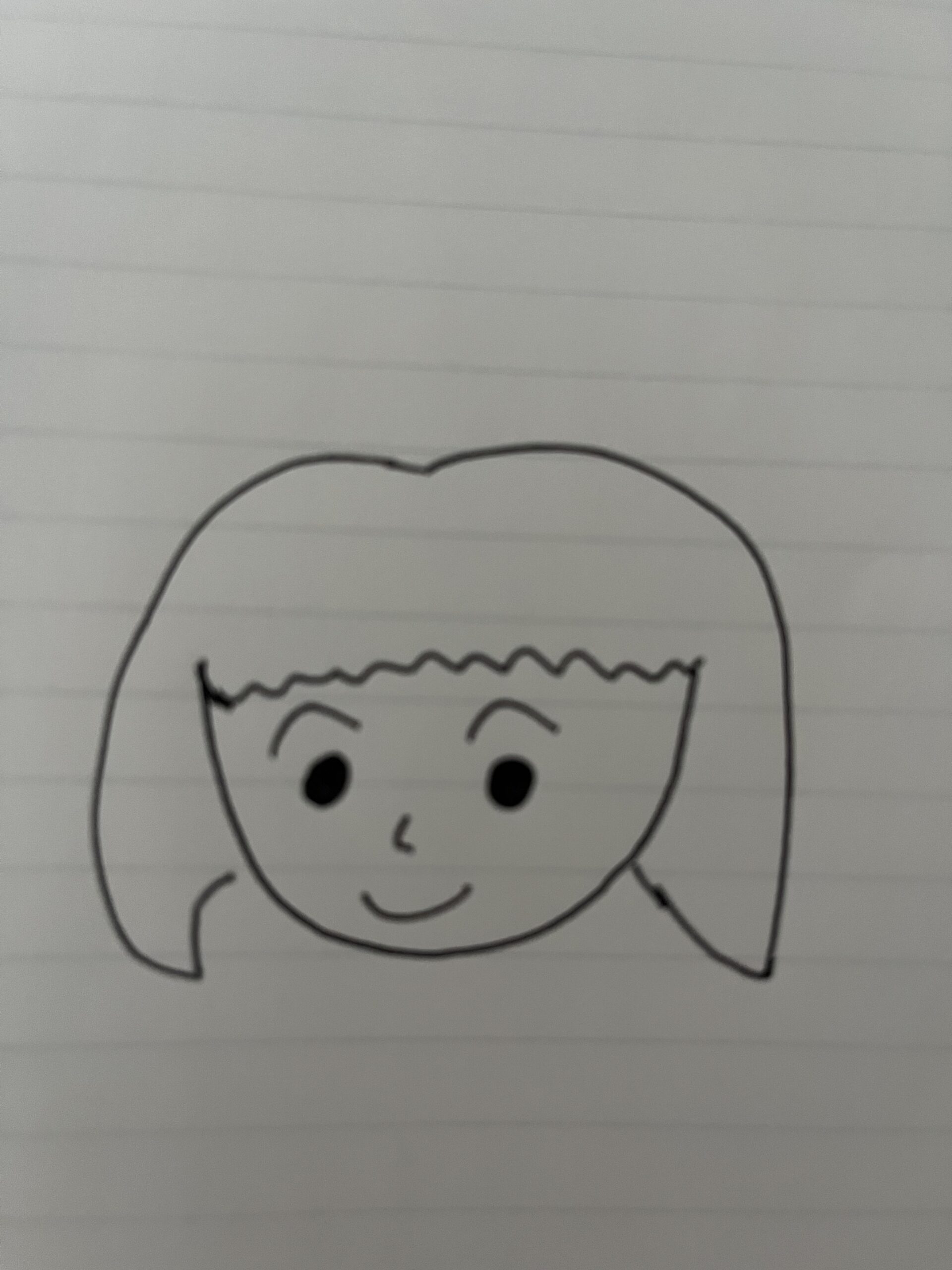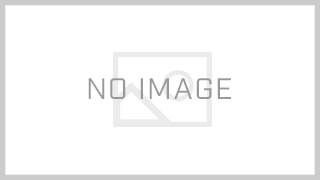前回の記事で、経済的自由への挑戦を再スタートし、目標金額と「最初に学ぶべき3つのテーマ」を設定しました。
正直、私は4年ほど前からNISA口座を「実践」していましたが、知識の裏付けがないまま放置している状態でした。今回の挑戦は、この「知っている」と「理解している」のギャップを埋め、投資に確信を持つことが目的です。
その第一弾として、今回は「新NISAとiDeCo」という日本の二大税制優遇制度の基礎知識を学びます。
1. 挑戦の原資を生み出す!生活防衛費と固定費削減
資産運用を始める前に、まず「生活防衛費」を確保し、土台を固めることが最優先です。そのために、毎月の支出を徹底的に見直しました。
【実践】固定費と変動費をダブルで削減
① 固定費(固定支出)の見直し
意識しないと垂れ流しになりがちな固定費は、一度見直せば永続的に効果が続きます。読者の方もできるように、私が見直し対象とした項目を具体的にリストアップします。
| 見直し対象 | アクションの例 |
|---|---|
| 通信費 | 大手キャリアから格安SIMへの乗り換え、またはプランの確認。 |
| サブスクサービス | 毎月引き落としリストを作成し、「本当に週に1回以上使っているか?」を基準に解約・休止。 |
| 各種保険 | 生命保険や医療保険について、保障内容の過剰がないかを確認し、ネット保険などと比較検討。 |
| クレジットカード年会費 | 利用頻度が低い有料カードは解約し、年会費をゼロに。 |
② 変動費(変動支出)の見直しと生活習慣の改善
この挑戦を始めてから、お金の使い方も意識的に見直しました。以前は仕事終わりに夫と駅で待ち合わせをして外食で済ませることも多くありましたが、最近は家でご飯を作るように心がけています。正確な節約額はまだ把握できていませんが、確実に外食費が減り、資産形成の原資を増やせている実感があります。
この結果、私が「不安なく生活できる期間」として確保すべき生活防衛費の金額を明確に算出し、土台ができたことで精神的な安心感を得ることができました。
2. 二大税制優遇制度の徹底比較:新NISA vs iDeCo
土台が固まったところで、いよいよ知識獲得のテーマ1に進みます。
Part 2-1: 資金の自由度が高い!新NISA(2024年〜)の徹底解剖
新NISAは、旧NISAのデメリットを全て解消し、「非課税期間の無期限化」と「生涯投資枠の復活」という二大メリットを得た、非常に強力な制度です。
| 項目 | 旧NISA(つみたてNISA) | 新NISA(2024年〜) |
|---|---|---|
| 制度期間 | 2018年〜2023年 | 恒久化(無期限) |
| 非課税期間 | 20年間 | 無期限 |
| 年間投資枠 | 40万円 | 360万円(つみたて枠120万+成長枠240万) |
| 生涯投資枠 | なし | 1,800万円(全員共通) |
| 売却後の再利用 | 不可(枠が復活しない) | 可能(非課税枠が復活する) |
【新NISAの2つの投資枠】
新NISAは以下の2つの枠があり、年間360万円まで併用可能です。生涯投資枠(1,800万円)は、どちらの枠を使っても減っていきます。
| 投資枠 | 年間上限額 | 主な対象商品 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 120万円 | 長期・分散に適した投資信託(S&P500、オールカントリーなど) | 初心者、長期でコツコツ積立をしたい人 |
| 成長投資枠 | 240万円 | 上場株式、ETF、REIT、幅広い投資信託 | 個別株投資や、自分で商品を選びたい人 |
【旧NISA資産の扱い】 私が旧NISAで投資していたS&P500やオールカントリーの資産は、新NISAの1,800万円の枠とは別に、非課税期間(つみたてNISAなら20年)が終了するまでそのまま運用が続けられます。この点は、すでに投資を始めている人にとって大きなメリットです。
【新NISAの始め方(シンプル)】
新NISAの口座開設は非常に簡単で、基本的に以下のステップで完了します。
- 金融機関を選ぶ: ネット証券(手数料が安く、商品ラインナップが豊富)か、銀行(窓口で相談可能)から選びます。
- 申し込み: 選んだ金融機関のウェブサイトで、オンライン申し込みを行います。
- 本人確認: マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提出します。(オンラインで完結することが多い)
- 口座開設完了: 税務署の審査を経て口座が開設されます。
- 商品選択・購入: 開設後すぐに、つみたて設定や商品の購入を開始できます。
Part 2-2: 最大の節税効果!iDeCoのメリットと制限事項
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金作りに特化した制度であり、その最大の魅力は「節税効果」です。
- iDeCoの3大税制メリットの具体例
- 掛金が全額所得控除:これが最大のメリットです。例えば、年収500万円の会社員が月2万円(年24万円)を積み立てた場合、その24万円分の所得税と住民税が軽減されます。年末調整で数万円単位のお金が戻ってくることもあります。
- 運用益が非課税:NISAと同様、利益がまるごと非課税で再投資されます。
- 受け取り時にも控除:将来60歳以降に一時金で受け取る場合、**退職金と同じ「退職所得控除」**が適用され、税金の負担が非常に軽くなります。
【iDeCoの始め方と手続きの流れ(手間がかかるが節税効果大)】
iDeCoは税金が絡むため、NISAと比べて手続きに少し手間と時間がかかりますが、毎月の積立額は月額5,000円から始められます。
- 金融機関を選ぶ: 証券会社や銀行など、iDeCoを取り扱う金融機関(運営管理機関)を選びます。手数料が安く、運用商品が良いところで選びましょう。
- 加入申込み: 選んだ金融機関を通じて、国民年金基金連合会へ加入申込みをします。会社員の場合は勤務先の情報も必要になり、書類のやり取りが発生します。
- 資格審査: 国の機関で加入資格の審査が行われるため、完了までに約1〜2ヶ月かかります。
- 掛金と商品設定: 審査完了後、毎月の積立額(上限あり)を設定し、運用商品を選んで積立がスタートします。
- iDeCoの掛金の上限額(目安)iDeCoは加入資格(職業や企業の年金制度)によって積立上限額が定められています。加入者の種別月額上限額(目安)企業年金のない会社員23,000円公務員12,000円専業主婦(主夫)23,000円自営業者など68,000円
- iDeCoのデメリットと手続きの注意点
- 原則60歳まで引き出し不可:老後資金専用のため、資金の流動性がありません。
- 手続きの手間:加入時に審査が必要で、その後も毎年、税制優遇を受けるために年末調整(会社員の場合)または確定申告(フリーランスの場合)の手続きが必要です。
- 住宅ローンとの関係:iDeCoの所得控除と住宅ローン控除(税額控除)は併用が可能です。
Part 2-3: 私がiDeCoを「見送る」理由(選択と集中)
iDeCoの節税効果は非常に魅力的ですが、私は今回の挑戦においては新NISAに集中することを選択しました。
【判断理由:資金の流動性を優先】 私の最大の目標は「お金のために働かない状態」を早期に達成することです。資金が60歳まで固定されてしまうiDeCoよりも、いつでも引き出し可能で、かつ生涯1,800万円という大きな枠を持つ新NISAで資産の最大化を目指す方が、今の私には合っていると判断しました。
3. まとめと次の予告
今回の学習で、新NISAとiDeCoの制度と違い、そしてその特性を踏まえた上で「新NISAに集中する」という明確な判断を下すことができました。また、その原資を生み出すための固定費削減の具体的アクションも確立できました。
次の記事では、いよいよ投資の根幹となる知識に進みます。
次回は、リストアップした「テーマ2:インデックス投資とは」に焦点を当てます。なぜ私がS&P500やオールカントリーを選んでいるのか、その確信的な理由を深く理解し、ブログで共有する予定です。
また次回の更新でお会いしましょう!