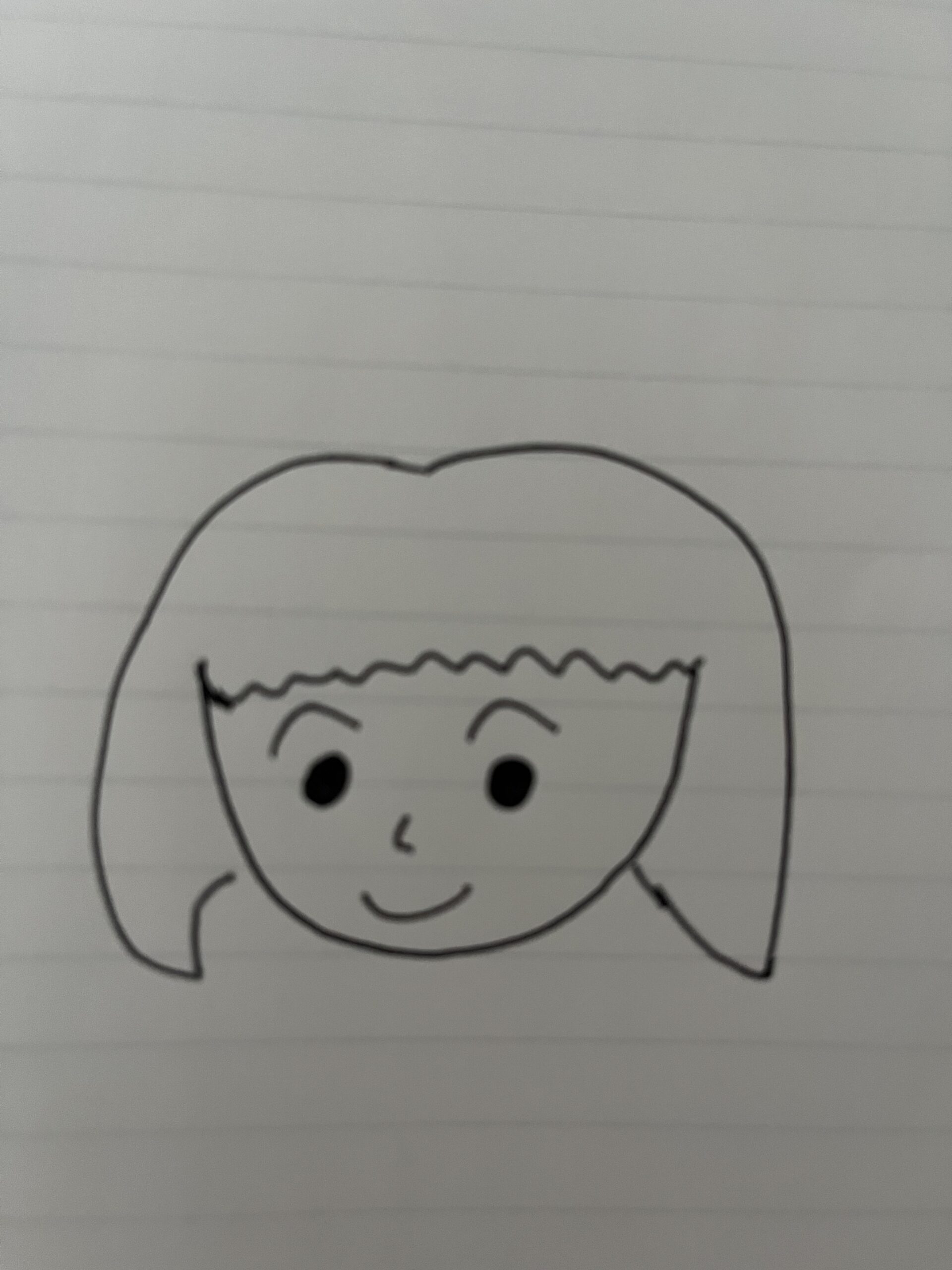1. はじめに:最高のタイミングで訪れた「断捨離の機会」
皆さん、こんにちは!単身赴任の準備に追われている最中ですが、このバタバタこそが、我が家にとって最高の「断捨離の機会」になっていることに気が付きました。
普段は「まだ使える」「いつか使うかも」と、なかなか手放せないモノたち。特に年末の大掃除と重なったことで、「今、動かせないモノは、これからもいらないモノ」だと、思考がクリアになったんです。
今回は、この引っ越し準備をきっかけに、長年溜め込んでいた「捨てられないモノ」を潔く手放すことができた、私の3つのマイルールをご紹介します。
2. 単身赴任準備をトリガーにした「手放すための3つのマイルール」
2-1. ルール1:「単身赴任の終着点」ルール
夫の単身赴任先に持っていくモノを考える際、「これは単身赴任が終わったら捨てる予定のモノ」と潔く定義しました。この戦略のおかげで、私たちは「まだ使えるけれど、家に置いておくにはストレスだったモノ」を手放すことができました。
- 具体例: 古い食器、使い古したタオル、穴が開くまできていた下着などの消耗衣類、そして取っ手が壊れて使いづらくなっていた引き出しなど、「機能はしているが、使用時にプチストレスを感じるモノ」を優先的にリストアップしました。
- 収納家具の持ち出し戦略: 単身赴任先(レオパレス等)に備え付けがない収納系の家具(前の家から持ってきたものの、自宅ではサイズが合わず持て余していたハンガーラックや衣装ケースなど)も、このルールで持ち出すことを決意しました。これらは、単身赴任期間が終わったら現地で処分(不可の場合は自宅に持ち帰って粗大ごみで処分)することを前提としており、自宅の収納を改善するきっかけとなりました。
- 効果: 「自宅の買い替えの口実」になり、「まだ使えるから…」という罪悪感が解消されます。モノを最後まで使い切るという満足感も得られます。特に、壊れかけの引き出しのようにストレス源だった家具を処分し、自宅に新しい、サイズ感の合った収納を取り入れることで、見た目の統一感と使い勝手が劇的に改善されました。
2-2. ルール2:「過去の栄光」ルール
「痩せたら着る服」「いつか使う高価な教材」など、過去の目標や栄光に縛られて手放せないモノに対して適用しました。
- 具体例: 5年前のスーツ、使わなくなった高級ブランドの箱、読み切れていない専門書など。
- 【本棚の決断】 このルールで最も大きな決断が本棚の処分です。家にある本はほとんど2回目を読むことがなく、最近はKindle(電子書籍)に完全に移行したため、大きな本棚自体が「スペースの贅沢な占有者」だと判明しました。冷静に考えると、本棚が占めている床面積にも毎月家賃が発生しています。その空間コストを考えれば、デジタル移行は非常に合理的な判断でした。
- 電子化のメリット 物理的なモノと異なり、電子データはデータ容量は使うものの、物理的な収納スペースを一切消費せず、管理が非常に楽です。検索性や持ち運びの利便性も考慮すると、今後もKindleをメインに利用していくのが賢明だと判断しました。
- 【本棚の決断】 このルールで最も大きな決断が本棚の処分です。家にある本はほとんど2回目を読むことがなく、最近はKindle(電子書籍)に完全に移行したため、大きな本棚自体が「スペースの贅沢な占有者」だと判明しました。冷静に考えると、本棚が占めている床面積にも毎月家賃が発生しています。その空間コストを考えれば、デジタル移行は非常に合理的な判断でした。
- 効果: 「過去の自分に感謝し、未来の自分にスペースを譲る」と考えることで、手放すことをポジティブに捉えられました。
2-3. ルール3:「1ヶ月以内に触ったか」ルール
一番シンプルなルールで、「この1ヶ月間、意識的にこのモノに触って使ったか?」を自問自答しました。引っ越し準備でモノを移動させているだけの「受動的な接触」はノーカウントです。
- 具体例: 棚の奥に入っている調理器具、年に一度の来客用食器、趣味のコレクションの一部。
- 【衣類の断捨離】 特に衣類は、季節の変わり目に整理することで、「なんとなく置いてあるだけで、実はなくても生活に支障のないモノ」を明確に捨てることが決意できました。実際、着ている服はいつも同じものが多く、高価な服を「もったいない」と感じて着ていないことに気づきました。
- 効果: 使用頻度が明確になり、迷いがなくなります。使っていないモノは、引っ越しの手間とスペースを奪う「負債」だと認識できます。
3. 実践のコツ:断捨離の「決断疲れ」と「モノの増加」を防ぐ時間術
断捨離を成功させるためには、マイルールだけでなく「実行の仕方」と「モノの増やし方」を見直すことも重要です。
3-1. 「分割」して「一晩寝かす」戦略
- 私は「朝の1時間だけ」など、時間を区切って断捨離を進めるようにしました。時間が取れないという問題も解消されます。
- この「分割」の最大のメリットは、心の整理ができることです。昨日、感情的に「捨てられないかも」と収納に戻したモノも、一晩経って冷静になると「やっぱり、もういらないな」と判断できるようになりました。少しずつ、時間をかけて向き合うことが、結局は一番の近道でした。
3-2. モノを増やさないための「買い物マインドセット」
- 断捨離をしていて痛感したのが、「安いから買っておこう」という理由で手に入れたモノは、結局のところ本当に欲しいモノではないため、家に眠ったまま使われないことが多いという事実です。
- 【ネットショップの罠に注意】 特に最近は、ネットショップで「ポイントがもらえる」「今だけセール」というお得感に惹かれて購入してしまうことが多くありました。しかし、これらも欲しいものではないため、開封すらされず、ただ家にあるだけのものが多いことに気づきました。
- 【モノの価値=使用頻度で考える】 断捨離を通して、本当に必要なモノとそうでないモノを冷静に見極める力がつき、衝動買いがほぼなくなりました。モノの価値を「価格」だけで判断するのではなく、「安くても目的を果たせるもの」と「高くて長く使えるもの」のどちらが自分にとって最適かを、使用頻度と目的を軸に深く考えるようになったのが最大の変化です。高価なモノは品質が良い反面、「もったいなくて使えない」というデメリットが生じ、結果的に使用頻度が低い「負債」になりがちです。これからは、「安いから買う」のではなく、「いつ使うのか」まで想像し、「欲しいから(必要だから)買う」というマインドセットに切り替えることが、最も効果的な断捨離の予防策だと気づきました。お店やサイトで一度立ち止まって考える習慣が、未来の散財とモノの蓄積を防いでくれます。
4. まとめ:断捨離は「未来の快適さ」への投資
引っ越し準備と断捨離を同時に進めるのは大変でしたが、この機会がなければ、まだまだモノに埋もれた生活を続けていたかもしれません。
今は引越しの段ボールなどがあり、まだ断捨離をした実感が実はわいていませんが、引っ越しが完了したら段ボールなどもなくなり、ものも少なくなるため家が広く感じると思っています。
家電レンタルで「処分に困るモノ」を持たない選択をしたように、モノを手放すことは、「未来の自分がより快適に過ごすための投資」だと感じています。モノが減った分、年末の大掃除の負担も軽くなり、ゴミやリサイクルとして分別していく過程で、実際にモノが減っていくのを目で見て確認できるため、気持ちが本当にスッキリしました!
何よりも、モノに縛られない身軽な気持ちになれたことが、この断捨離の最大の収穫だと感じています。
さらに、モノを移動させたことで、普段の掃除では手が届かない家具の裏や部屋の隅など、家の汚れの盲点にも気づくことができました。断捨離を終えた後は、この気づきを活かして、年末の大掃除を徹底的に進めたいと思います。
皆さんも、引っ越しや大掃除など、大きなイベントがある際には、ぜひこの3つのマイルールと「分割戦略」、そして「買い物マインドセット」を試してみてください。次の記事では、実際にレンタル家電が届いたレポートをお届けする予定です。お楽しみに!